【第8回】矢澤一良博士が行く!ウェルネスフード・キャラバン【えがお】
えがお代表取締役会長兼社長
北野忠男氏
矢澤一良博士(早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所ヘルスフード科学部門 部門長)が「ウェルネスフードのこれから」を探る対談企画「矢澤一良博士が行く!ウェルネスフード・キャラバン」第8回は、健康食品の販売で知られる通販大手「株式会社えがお」の北野忠男代表取締役会長兼社長にご登壇いただいた。社是に「感謝」を掲げ、地元熊本県における地域産業活性化にも貢献しているえがお。陣頭指揮を執る北野代表は、お客様応対専門スタッフ「ラピネス」と製品価値を結び付けるえがおの強みについて語り、矢澤博士はその視点に大きくうなずいた。生活者が健康食品に親しむ場は「店頭」「EC」に留まらない。「えがおはいったいどうやってロイヤルカスタマーを獲得しているのか」―――その核心に矢澤博士が迫る。【記事=中西陽治】

「食の栄養価低下」の危機感がサプリメントのスタートに
矢澤一良博士(以下、矢澤博士):健康食品通販のリーディングカンパニーであるえがおさんですが、その創業のきっかけにつきましてお伺いします。
北野忠男代表取締役会長兼社長(以下、北野氏):当社創業は1989年で、当時はまだ日本で健康食品が認知されていない時代でした。

創業当時は皮革製品輸入・海外製品の直輸入を行っていましたが、以前から私は「これから健康はもっとも重要なプライオリティだ」と考えていたのです。私の家族が病に伏せた時、薬だけに頼らず元気になれるものはないかと、強く感じるようになりました。
こういった複合的な状況がある中で、2000年に初のオリジナル健康食品「にんにく卵黄」を発売し健康食品にチャレンジしました。
矢澤博士:北野社長は今から25年前に「健康が今後大きなキーワードになる」とお考えになった。当時は、2025年問題にもあるような少子高齢化すなわち人口動態の変化が急速に進むと言われていました。特に生活習慣病が顕在化する時期でもありましたね。
北野氏:おっしゃる通りです。やはり病気にならない体をつくることが幸せにつながりますし、健康な人が増えることで年々上昇する社会保障費に歯止めがかけられる、と思います。壮大な話ですけれども。
矢澤博士:健康を維持するための「食」についても選択肢があります。えがおさんは熊本県に本社を置いています。熊本県は畜産物も水産物も豊富で、美味しい野菜や果物が育つ地です。
その中で、サプリメント形状の健康食品に着手した思いとは。
北野氏:私は健康になるために必要なのは「食」と「運動」と「睡眠」、そして「ストレスコントロール」だと思っています。
創業当時、私は「食の栄養価が下がっているのではないか」と感じていました。ですからサプリメントで補うことが重要になってくると考えたのです。
ひとつの例として「黒酢」があります。黒酢は日本において200年以上前から飲まれているものの、そのまま飲むと飲みづらさを感じることがあります。そこで健康のためには飲みやすく、続けやすい形にしていくべきだと考えサプリメントという最適な形に落とし込みました。
また、当時も感じていたことですが、日本はサプリメント先進国のアメリカに10年は遅れています。おそらく今もそうでしょう。
けれどもアメリカのサプリメントは大型で飲みづらい、という声もありました。ならば、日本人の嗜好にあった飲みやすいサプリメントを作るべきだと思いました。
矢澤博士:確かに、「黒酢が体に良いことはわかっている」けれども飲みづらさのためにその価値が伝わり切っていない、あるいは途中離脱してしまうことは、健康になりたい人にとって機会損失ですね。
おっしゃるように人間の寿命が延びると同時に、栄養素として足りない成分が増えてきています。これまでの食では補いきれない栄養を補充していく、という観点に立たれているのですね。
「人の健康に関わる最も重要な仕事をしている」を社内教育で伝える

矢澤博士: 2003年に私は東京海洋大学(元・東京水産大学)でヘルスフード科学(中島董一郎記念)寄付講座を開設しました。2012年に10年にわたる寄付講座を終えた時に、北野さんにご相談させていただき、新たに2年間の寄付講座を立ち上げていただきました。
私の研究活動や学生の教育は当然ながら、何より社会貢献を力強くサポートしていただきました。そのご恩とご縁があり、今日に至っています。
北野さんは、研究や開発も大切にしていらっしゃると思います。
北野氏:矢澤博士とのご縁がありまして、大学とのかかわり、研究のサポートの重要性を強く感じました。
同時に教育を通じて健康へとつなげていく大切さも再認識しました。研究と教育が健康意識を高め社会に還元していく、という好循環を生むということです。
矢澤博士:その話に関係するのですが、北野さんは「教育」を非常に重要視されています。通信販売という業態で考えるとコールセンターは重要な心臓部にあたると思います。そこで大きな役割を果たす「教育」という観点に至った経緯につきましてお伺いします。
北野氏:「教育」があるからこそ日本を支える人財を生み出すことができると思っています。
小学生の子どもたちに話す機会があるのですが、「教育はとにかく大切です。だから知識を身につけましょう。お金は無くなるけれども知識は無くなりません。知識は人生を支えるので、お金が無くなっても知識があればまた豊かな生活を目指せます」と伝えています。
健康食品の活用についても教育は大切です。健康とは何か、についてまだご存じでない方に対してわれわれはしっかりとお伝えしていかなければなりません。
「われわれは健康に関してのコンサルティングをして、お客様が理解を深めて健康になっていただく」。その意味でスタッフに対して、「人の健康に関わる最も重要な仕事をしているのです」ということを伝えています。
矢澤博士:えがおさんの熊本本社には「私たちは 世界の人々に健康と笑顔を 提供し続けることを通して 広く社会に貢献すると共に 全社員の幸福と成長を追求する」という経営理念が掲げられています。
この〝広く社会に貢献する〟という点が、健康に関わる人間が心に刻まなければならないことだと思います。
もうひとつが、仕事を通じて共に成長する社員さんの「物心」の部分です。お金もそうですし、心の豊かさの両面での幸福を通じて、一緒に成長していく、ということでしょう。
北野さんは教育も含めて「社員を大事にする」と考えておられる。この点についてどのようにお考えでしょうか。

北野氏:〝はたらく〟ということは自己実現でもあると考えています。自己実現には色々な方法があると思います。例えば、お金のために働く、ということも一つの方法でしょう。プロセスはさまざまですが、最終的な自己実現は〝幸せ〟にこそあるのです。
働くのは幸せになるためです。その働く目的を全社員が共通理解し、幸せになるために働く。
お客様に幸せをお届けするために、社員が幸せであることが大切だと思うのです。
えがおの魅力をダイレクトに伝達する「ラピネス」の存在価値

矢澤博士: えがおのコールセンターで働くお客様応対専門スタッフは「ラピネス」(※)と呼ばれます。
いつも「ラピネス」へどのようなメッセージを伝えていますか。
(※)「ラピネス(Rappiness)」とは、「架け橋」を意味するラポート(Rapport)と、「幸福」を意味するハピネス(Happiness)をかけ合わせてつくられた、えがおにおけるコミュニケーターの名称。
北野氏:「ラピネス」は、お客様に喜ばれることにコミットし、それが自らの喜びと感じるマインドを持っています。
「ラピネス」にも、「われわれは健康を通じて人々を幸せにする、大義ある仕事をしています」という矜持を伝えてきました。それが「ラピネス」たち社員の、働く笑顔の源になっているのならとても嬉しいことです。
矢澤博士:えがおさんは、九州の学生の就職志望先としてもかなり上のランクに位置しています。それは幸福に直結する社名や「ラピネス」から伝わる社風が、生活者に浸透している、ということでしょうね。
北野氏:ありがとうございます。
えがおの事業は、健康に携わるものです。しっかりとその価値を伝える「ラピネス」の存在はえがおにとってかけがえのないものです。
新卒社員のご両親にも「えがおの健康食品はいいよね」と感じていただいています。
健康食品への捉え方がポジティブになった世代が、子を持つ親となったことも関係していると思います。今まで積み重ねてきた「健康の伝達」が本当に評価される時代にきたと実感しています。

働く従業員のために幼稚園を開園
北野氏「相手の立場に立ってこそ『安心感』を提供できる」
矢澤博士: 教育と社会貢献につながるエピソードについて一つ。えがおさんは幼稚園を開園されましたね。お子さんをお持ちの「ラピネス」を支援する目的でもあるのでしょうか。また、「ラピネス」は女性が大多数です。その子育て支援と女性支援について、どのような観点で行っていらっしゃるのか。

北野氏:幼稚園を開園した理由には2つあります。
1つは地域社会を見た時「幼稚園が少ない」という現実です。これはどうにかしなければと思いました。
2つ目は、働く人たちの環境づくりが大切だと感じているからです。おっしゃるように「ラピネス」には女性が多いので、子どもがいても働ける環境を作るべきだと思ったのです。その環境づくりこそが〝はたらく喜び〟に直結するのです。
働きながら幼稚園の送り迎えは大変でしょう。職場の近くに幼稚園があれば安心して働くことができます。
矢澤博士:働くうえでの〝安心感〟は素晴らしい価値だと思います。
生活者が感じる「ラピネス」への安心感は、信頼につながる唯一無二の価値でしょう。
北野氏:働く人の立場に立って会社を作っていかなければなりませんし、相手の立場に立たないと、その人が感じる「安心感」が何なのかはわかりません。その観点に立つことが、結果としてお客様の安心感につながると思うのです。
「お客様に喜ばれる」――えがおのコールセンターにしかできない強み
矢澤博士:お客様応対つまり「コールセンター」の差別化ポイントをもう少し深堀させてください。

私も大学で研究しながら、いろんな企業にお会いする機会があります。その中で「えがおのコールセンターの質の高さ」を評価する声がありました。
この「質の高さ」は、幸せに対するマインドを持つ、つまり本人の資質に頼る自然発生的なものばかりではないと思うのですが、いかがですか。
北野氏:そうですね。そもそも持っている素質もありますが、われわれも教育には力をいれていましたので、その要素も大きいと思います。ただモノを売るのではなく、商品の価値をお伝えすることが重要なのです。
モノを売るためだけに時間をかけるとコストになります。そうではなく「逆に時間をかけても良いからお客様とコミュニケーションをとってください」ということです。
通常のコールセンターはかかってきた電話をいかに時間内にこなすかが収益につながる、という考え方です。しかしわれわれはまったく違う観点に立ったアプローチなのです。「お客様に喜ばれる」ことが価値だという点は一切ぶれずにやってきました。
矢澤博士:「お客様に喜ばれる」ことが従業員の働き方ひいては幸福にもつながる。えがおさんの福利厚生にもそれが現れています。
余談ですが社員食堂の立派さに驚いたことがあります。リーズナブルな価格と美味しさを両立した献立には「従業員が健康でなければならない」という思いが現れていると感じました。栄養バランスとカロリーが計算されていますし、あの献立は他の社員食堂にはないと思います。
夕方にはその社員食堂の一角を居酒屋として開放し、そこで社員がコミュニケーションの場として利用している姿を拝見しました。これは斬新でした。
北野氏:社員居酒屋の「和話輪(わわわ)」ですね。
えがおはお客様に対してだけでなく、社内のコミュニケーションも大切にしています。社員食堂や社内居酒屋の食事を通じて、社員同士が人柄を理解し、それが仕事のパフォーマンスに還元される、というサイクルを生み出したいと思ったのです。そのためには場所も必要でした。社員も笑顔で過ごせる会社であるべきだと思うのです。
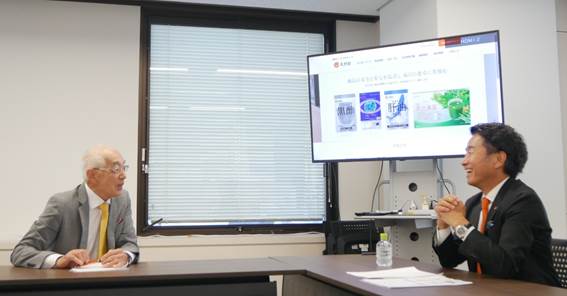
北野氏「新しい規制制度に対応できる会社が生き残っていける」
矢澤博士: 健康食品業界は規制が強化される向きもあります。これをポジティブにとらえると機能性表示食品あるいはトクホといった食品は次なる進化の過程にあると感じています。

規制という風当りは、私は業界にとってマイナスではないと認識しています。より生活者に安心と安全をお届けできるものへと発展をしつつある、と言えるでしょう。そうすると機能性などの制度について今一度考える時期に来ているのではないでしょうか。
北野氏:矢澤博士がおっしゃる通り、特に機能性表示食品ついて再考するタイミングにあると思います。
逆にその規制つまりレギュレーションを遵守することで、世の中から信頼を勝ち取れると思います。これは今以上の差別化ポイントだととらえています。
新しい規制に対応できる会社が生き残っていける、という意味でもあります。ほんとうの意味でサプリメントが世の中に信頼を持って定着していく。その過程にあると言えます。
矢澤博士: 通販、特にネット販売でのサプリメント販売が今後も増えていくと思われます。その点について。
北野氏:そうですね。われわれは品質の良さと機能にこだわりながら、安心して実感できる製品を作り、健康になっていただきたいと思っています。
当然ネット販売は広がっていくと思います。われわれは主なターゲットが65歳以上の方々ですが、今後は購買層が若い世代になってくるでしょう。
ネット購入に慣れている方、コールセンターを通じた通販を好む方、と細分化されていくと思われます。
また、ドラッグストアなどリアル店頭で購入される方は、イメージ重視で買われていることが多いと感じます。仮に店頭で購入されたお客様が、その商品について私たちのコールセンターにご相談いただいてもしっかりと説明できます。
ネット販売は、基本的に文字と画像での紹介となるため、ニュアンスが伝わりにくいところがあります。その点もコールセンターならば、安心して最後まで相談に応えることができるのです。またネット販売は利便性に特化しています。一方でお客様が求めているのは利便性だけとは限りません。それは、製品をお届けする人の〝温かみ〟と言いますか、言葉で伝える意義だと感じています。その両方を兼ね備えていくことが差別化につながるのです。
ネット販売もコールセンターの通販も、お客様のニーズに対して有機的に対応すべきです。
サプリと相互関係にある「えがおの食品」
矢澤博士:えがおさんではサプリメントだけでなく一般食品も取り扱っていますよね。これから一般食品の分野も広げていくお考えですか。
北野氏:はい。やはり「食で健康に」が基本です。トータルで健康になっていただくことがベースにありますから、一般食品とサプリメントが相互補完していく形でご提供していきます。
ですから取り扱う一般食品も、美味しくて健康をイメージできるような食でなければならないのです。高齢社会が進んでいくことを考えると、「食で健康」を担う私たちの事業は社会的な意義があると感じます。
30年後には日本の人口は1億人を割り、その4割が65歳以上の高齢者になると言われています。この30年後の日本社会を見据えると、私たちは健康長寿に資する〝食〟をお届けしていかなければならないのです。サプリメントも一般食品も社会貢献につながっていくのです。

矢澤博士:その通りだと思います。医療費を含む社会保障費にも限りがありますし、何より国民がなるべく病気にならないで健やかに歳を重ねていける社会を構築しなければなりません。
私が研究を進めている「食による予防医学」は〝医〟という言葉が入っていますが、薬やお医者さんにはフォローできない領域です。「食による予防医学」の目的は、病気にならないよう、あるいは病気になる前の期間を延ばして、天寿を全うできるようにすることです。
必要な栄養は個人差があります。単に店頭に置いてあるだけでは、どれが自分にあったものかが不透明です。そこに会話というコミュニケーションを挟むことで、個々人に適したものを提案できる。これは人の声、手を介してでしかできないことです。
北野氏:おっしゃるとおりです。
コールセンターでお客様の声に耳を傾け、その方が必要としてかつ求めている〝食〟をご提案しているからこそ、喜んでいただけていると実感しています。

コールセンターは商品の情報や栄養の知識といった技術ももちろん重要です。
お客様から、「他の会社で買った商品だけれども、えがおさんに聞いたら教えてくれると思って」というお声をいただくことがありました。これこそがえがおのコールセンターの価値だと思います。
〝えがおさんに聞いてみよう〟というお客様の期待と、それに対応する力と知識をコールセンターが持っているということを誇りに思ってほしいです。
仮に他社の製品についてのご質問であっても、われわれは丁寧にお答えします。これはコールセンターの職能発揮という意味でも、また「お客様の信頼を得る」という業界全体の信頼度向上につながるのです。
矢澤博士:リアル店舗には薬剤師も管理栄養士もいます。しかし薬剤師は薬のプロですから、どうしても対応が治療寄りになってしまう。管理栄養士に相談、となってもどこにアクセスすればいいかがわかりづらい。
そうするとコールセンターという距離や天候に左右されないアクセス方法は手軽ですし、商品知識や健康情報を持って対応する「ラピネス」は安心して相談できる窓口ですね。
私もウエルネスに携わる研究者として、「ラピネス」が持ちたい知識や、健康トレンドがあればお伝えしたいと思います。「ラピネス」が電話口の生活者に安心安全な情報を提供することが、健康産業の信頼獲得につながるわけですから。
北野氏:超高齢社会へと進んでいきますので、私たちとしても矢澤博士のアカデミックな観点はとても大切だと思っています。健康長寿を実現するためには、商品力はもちろん、その商品の研究およびエビデンス、それをお伝えするコールセンター「ラピネス」という職能が有機的に関わっていく必要があると思います。
研究が進む次世代型「黒酢」「鮫肝油」
矢澤博士:健康に関する食の研究について、実例をご紹介したいと思います。
北野社長には日本黒酢研究会でもお世話になっています。
黒酢は〝なんとなく体にいい〟〝アミノ酸や酢酸が豊富〟という理解レベルの素材でしたが、いまは研究発表の中で、そのエビデンスが明らかになっています。
第二世代研究が黒酢で始まろうとしています。「美容成分のアミノ酸が生体内に関与しているのでは」という視点から、「生体内で代謝された微量な成分に抗炎症作用がある可能性がある」ことが徐々に明らかになっています。
黒酢は発酵食品ですから、発酵の過程で様々な成分が生まれます。日本黒酢研究会ではそういった成分の一つ一つの効果を検証しています。発酵食品は奥深く、研究の余地が大いに残されています。
「健康のためになんとなく黒酢を飲む」から新しいステージに進んでいるということです。これも研究開発の中で追及していくべきでしょう。新規の素材や成分も魅力的ですが、いままさに栄養学では黒酢のような伝統食の最新研究も進んでいるのです。そうすると研究と開発の両面で〝次世代型の黒酢〟という全く新しいアプローチが生まれるでしょう。
北野氏:それはとても興味深いですね。
黒酢は長い歴史をもつ発酵食品ですから、信頼性はもちろん、健康に寄与することも明らかです。〝なぜ黒酢で健康になるのか〟がより明確になると、身近な食品として需要が高まると思います。

矢澤博士:もう一つは肝油、特に「鮫肝油」です。
「鮫肝油」に含まれるアルコキシグリセロールの機能についての研究が盛んになっています。主に脂質の一種であるスクアレンとのコンビネーションについてです。
以前はスクアレンの純度を上げるほどよい、とされていました。しかしその高純度生成のために廃棄されていたアルコキシグリセロールにも健康作用が期待される、という考え方にシフトしつつあります。
「黒酢」や「鮫肝油」など伝統的商品に含まれる成分であったとしても、われわれアカデミアからみるとまだまだ解明されていないメカニズムやマテリアルがあるのです。私はこれを楽しみにしていますし、研究者として実証したい、と熱意を込めています。
単に〝なんとなく健康にいい〟という考えから、その中身を明らかにし、より良い健康の実現〝ウエルビーイング〟につなげていく必要があると強く思うのです。

北野氏:メカニズムやエビデンスは、「食による予防医学」の根幹ですし、健康につながるものですから、私もとても興味があります。
安心・安全な商品を作ること。そして優れた商品をお届けするためにエビデンスを明らかにすること。これはお客様に商品を通じて健康をお届けする上でたいへん重要です。
ですが商品による健康の実現と同時に、お届けする価値も重要だと思います。ある種の心の安寧と言いますか〝安心して健康になれる、心の豊かさ〟です。安心して健康になっていただきたいから、しっかりとした説明・相談プロセスを踏んで商品をお届けする。この安心感はまさに〝ウエルビーイング〟に欠かせません。
矢澤博士:本当ですね。
研究がピカイチであっても、それで本当に幸せになれるのか。人のメンタルや取り巻く環境は複雑です。そこに〝温かさ〟や〝幸せ感〟がなくては本当に心身共に満たされた状態とは言えないでしょう。
えがおさんのますますの発展と、「ラピネス」の活躍に期待しております。
――ありがとうございました。





































