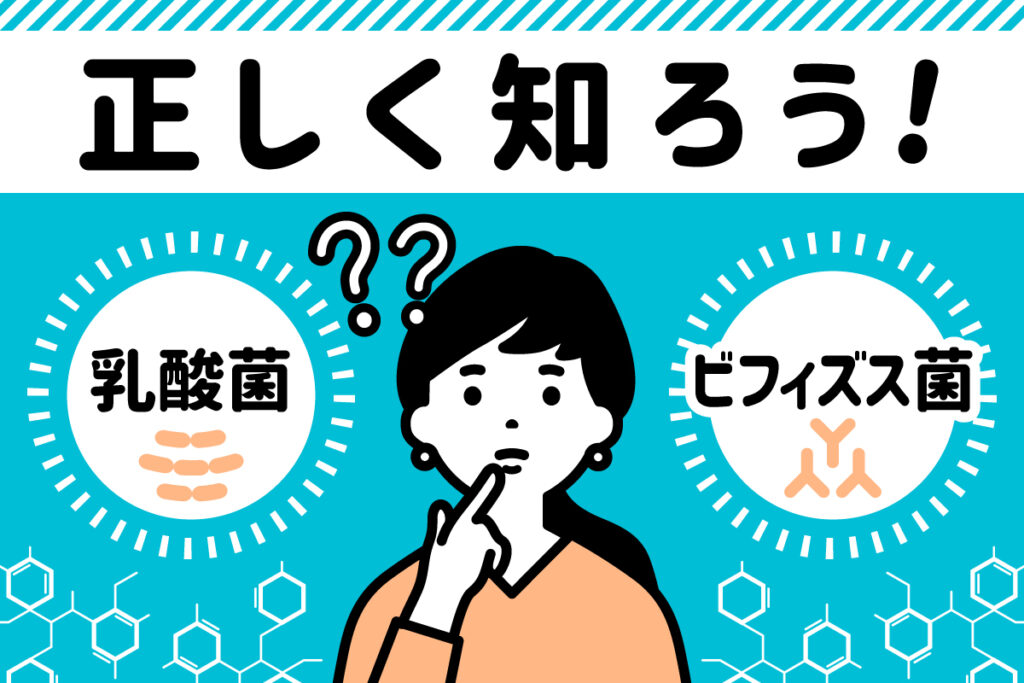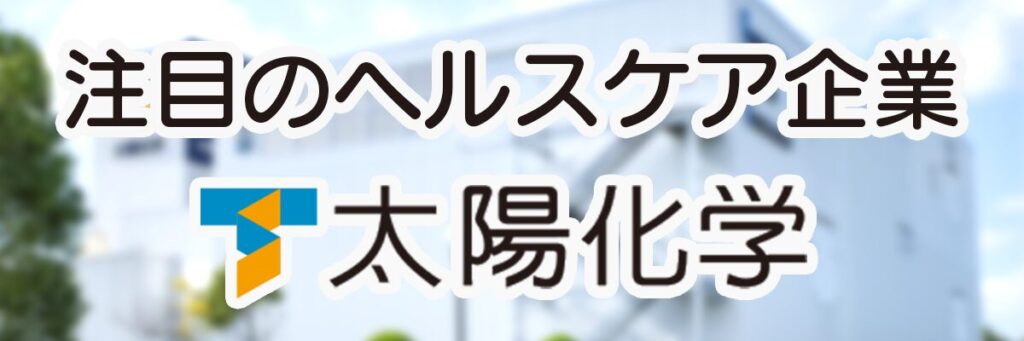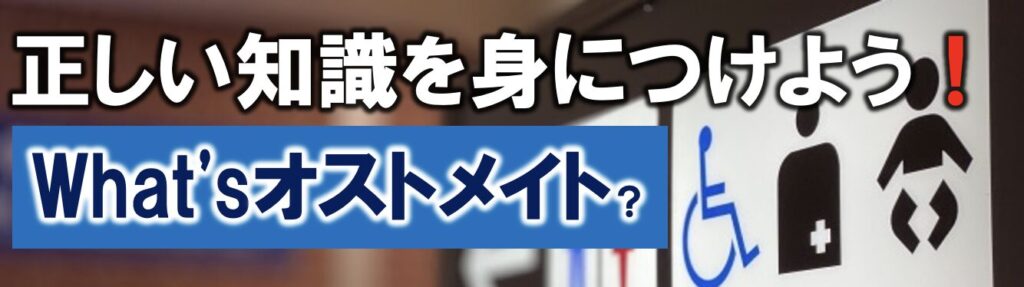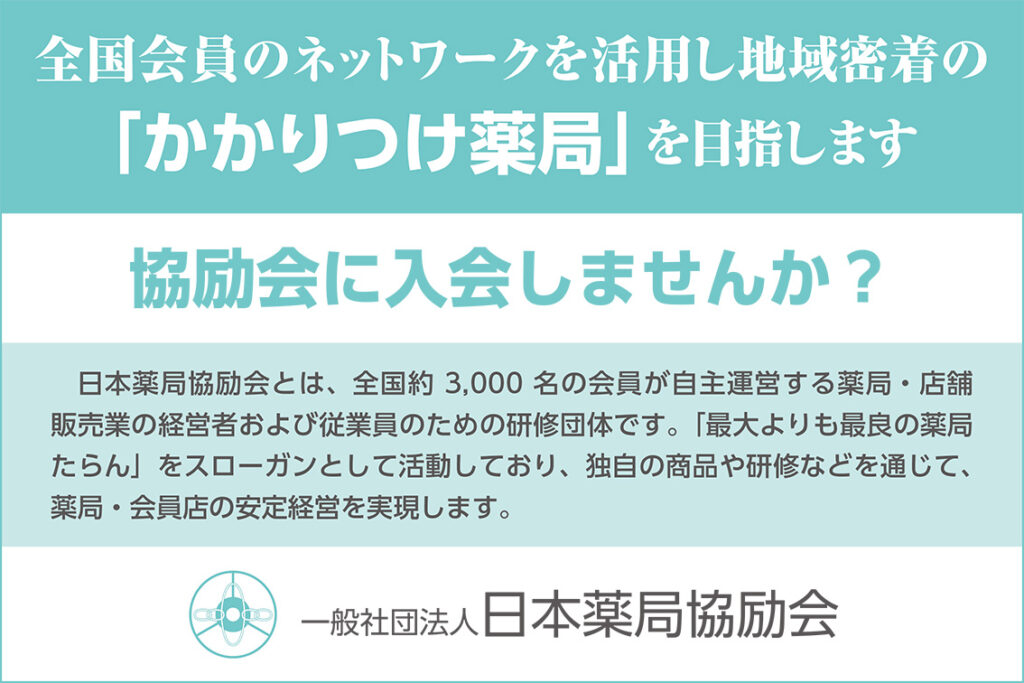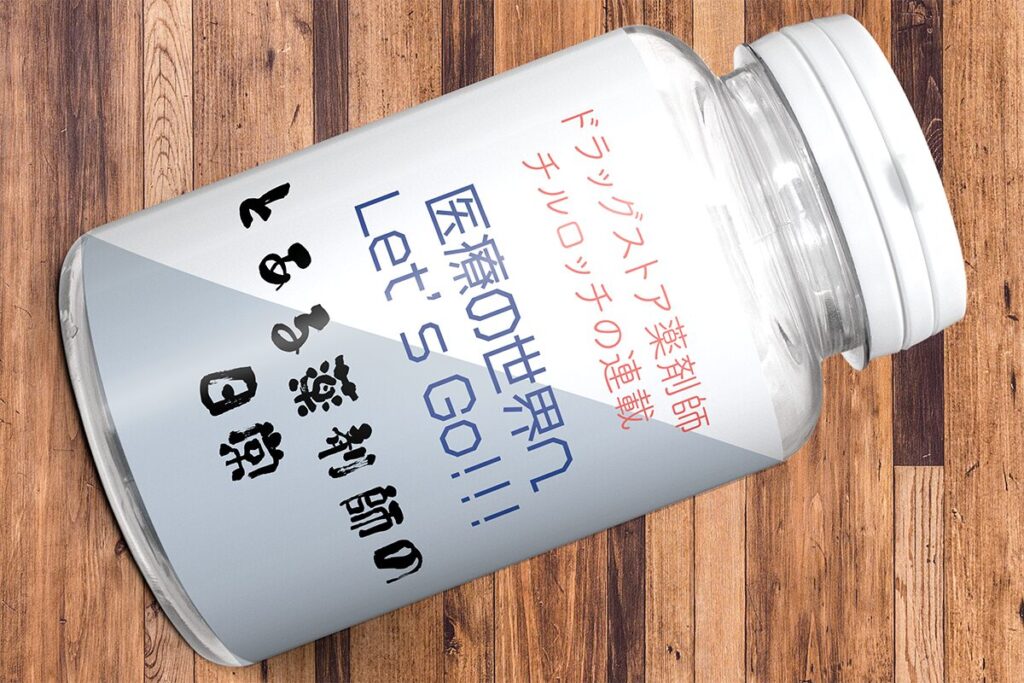アサヒ×ピップ対談企画〜少子化進むベビーフード市場を考える
子育て世代の切実な想いに応えた商品が登場
〜ベビーからトドラーのラインロビングで売場活性化を

少子化の中でも緩やかに拡大を続けるベビーフード(離乳食)市場。背景には、共働き等で家事時間に余裕のない親達の、「時間をかけずに高栄養で美味しい食事を提供したい」という切実な想いがある。近年、その想いが離乳期間(〜1歳半)を過ぎた子供の親にも及んでいるという。これに着目したアサヒグループ食品(川原浩社長)は今秋、1歳半〜3歳未満を対象にした新ブランド「ぱくぱくプレキッズ」を投入した。日本でも拡大が見込まれる「トドラー」市場を、食の領域から支えていく考えだ。当編集部はこのほど、同社とベビーカテゴリーの提案で定評のある卸売業・ピップに対談していただき、ベビーフードの現在地と将来性、市場拡大に向けた課題について語ってもらった。(取材と文=八島 充)
対談者
アサヒグループ食品株式会社
マーケティン部本部マーケティング四部・部長
高橋 岳春 氏
ピップ株式会社
執行役員マーケティング本部長兼MD部長
木村 徹 氏
120年に渡り乳幼児の成長見守ってきた和光堂
ベビー専門店開業の歴史を持つ卸売業・ピップ
――アサヒグループ食品の事業概要とベビーフードの位置付けを教えてください。

高橋 岳春 氏
高橋 当社はアサヒグループの食品事業会社として、アサヒフードアンドヘルスケア、和光堂、アマノフーズが合併して2015年に誕生しました。現在は「おいしさ+αを追求し、心とからだの健やかさの実現に貢献する」という長期ビジョンのもと、 “多刀流”すなわち幅広い食品群のそれぞれに磨きをかけるべく各事業を強化しています。
私が所属するマーケティング四部は、ベビーとシニアを守備範囲として、商品開発から販促までを担っています。創設10年とまだ若い会社ですが。ベビーは和光堂(1906年創業)から数えて100年以上の歴史があり、長く日本の乳幼児の成長をサポートしてきました。ラインアップは育児用ミルク、ベビーフードから、シッカロールやスキンケアなどで、乳幼児ケア商品・用品を幅広く扱っています。
――マーケティングに携わる前は広域量販の営業をされていたとか。
高橋 はい。ピップさんとも営業を通じて関わってきました。いくら良い商品でも、小売業様に優位性が伝わらなければ店頭に並びません。その上で売場づくりに深く関わる卸売業の存在は大きなものがあります。異動後も、卸経由の流通を意識しながら、マーケティング活動に取り組んでいます。

木村 徹 氏
――歴史の長さはピップも和光堂に引けをとりませんね。
木村 前身の藤本眞次商店は1908年に大阪で創業しました。当時は医療衛生材料を中心に卸していましたが、1969年発売の「シャンプーハット」のヒットなどを受け、自社製品の開発も積極的に行ってきました。72年発売の磁気治療器「ピップエレキバン」は、現在も当社の看板商品です。
卸売事業はヘルス、ベビー、シニア、コンフォートの4カテゴリーを軸にメーカーと自社を合わせた商品を提案しています。あまり知られていませんが、当社は1967年にベビー用品専門店(「フジベビー」)を開業したこともあり、ベビーカテゴリーには相当の思い入れがあります。
ピップ「ベビーカテゴリーの提案を通じ社会に貢献する」
アサヒグループ食品「ベビーフードの提供環境を守り続ける」
――ベビー、またシニアのカテゴリーは、商品の幅が広く回転率の差も大きいので、(倉庫から店頭への)配送効率が必ずしも良いとは言えません。
木村 だからと言って配送を滞らせて、商品を求める生活者に不便をかけさせることはできません。少子化が進んでも子供に良いものを与えたいというニーズは普遍であり、当社の取引メーカーさんもそうしたニーズに応えた商品群が増えています。「ベビーカテゴリーの提案を通じて社会に貢献する」という想いを持って、全国津々浦々に商品を届けることが当社の使命と心得ています。
――ベビーフードの開発には、嗜好性はもちろん栄養価や安全性といった食品特有の課題も伴います。
高橋 レトルトパウチのように回転率の高いものから、そうでないものも含めて、安全で美味しい、しかも成長時期ごとのラインアップが求められるという点で、メーカーの対応力が問われるカテゴリーだと思います。培ってきた技術を用いて子供の成長に貢献したいという想いは、ピップさんの理念と重なるものがあります。
――キユーピーが2026年8月末でベビーフードの製造販売を終了するというニュースが流れましたが、その受け止めを聞かせてください。
木村 長年市場を牽引されてきた功績に敬意を払うとともに、残念な想いをしているというのが正直なところです。ベビーフードを必要とされる生活者に影響が出ないよう、当社としても売場提案を改めて強化していく所存です。
高橋 同業の立場から、苦渋の決断であったものと推察します。また、ニュースを受けて、「10年、20年先も変わらずにベビーフードを提供する環境を守り続けよう」という決意を新たにしました。
――ベビーフードの市場自体はコロナ禍を経て堅調に推移しています。

高橋 2017年〜2024年の7年間で、出生数は94万人から68万人と3割弱減った一方、当社調べでは、ベビーフードの売上は26%増と、育児用ミルクの売上(15%増)以上の伸びを示しています。子供1人あたりの購入個数、購入頻度ともに増えているという認識です。その背景には、女性の社会進出に伴う家事時間の減少や、育児に参加する男性の増加等による簡便性ニーズの高まりがあると考えられます。
木村 育児休暇を取得したであろう父親が、ドラッグストアでオムツを購入するシーンも増えていますね。相対的に男性は価格に捉われず良いものを購入する傾向があるので、男性客の増加はベビーカテゴリーにもプラスの影響が出ると思います。ただ、ここ数年はインバウンドや値上げによる単価上昇が数値を押し上げているのも事実です。少子化の中でさらに市場を盛り上げるには、新たなアプローチも必要だと感じています。
「これからどうやって食事を与えれば良いの?」
〜「ぱくぱくプレキッズ」誕生の背景
――ベビーフードの新たなアプローチとして、アサヒグループ食品がこの秋に発売した新ブランド「ぱくぱくプレキッズ」が注目されています。開発の経緯をお聞かせください。

高橋 ベビーフードは主に生後5ヶ月〜1歳半に与える食事で、1歳半を過ぎると提供できる商品が極端に少なくなるのが実情です。またこの時期は育児休暇からの復職が増えるタイミングでもあり、対象となる親御さんから「これからどうやって食事を与えれば良いのか」と言う声が届いていました。

そこに着目した当社は、1歳半〜5歳までを「プレキッズ」期間と定め、課題の解決に取り組むことを決めました。第一弾として、1歳半〜3歳未満を対象にした「ぱくぱくプレキッズ」というシリーズを上市しました。発売後の反響が最も大きかったのは、意外にも「骨とりさばの味噌煮」でした。そのネーミングから、魚の小骨取りに負担を感じる“タイパ重視”層にも受け入れられたのだと思います。
木村 「魚を食べさせたい」と言う親心も作用しているのでしょう。何より「美味しそう」と思わせるパッケージデザインが秀逸ですね。
高橋 ありがとうございます。実際に専門家に監修していただいており、栄養価はもちろん味や食感にも自信があります。食の嗜好性が高まる大切な時期に、ぜひ食べていただきたい商品となっています。

――「プレキッズ」で新カテゴリーを開拓するという発想は、ピップの商品提案に通じるものがありますね。
木村 おっしゃるように、当社は「エイジアップ」をテーマに、既存カテゴリーのラインロビングによる売場の活性化を提案しています。未就学の5歳までを「キッズ」と位置付け、成長過程に合わせて切れ目なく商品を提案し、ベビーカテゴリーを目的に来店されたお客様に、継続して店舗を活用していただく狙いです。
昨年の展示会(ピップウエルネスフェスタ)では、親子連れの来店を想定し、バータイプのスナックやゼリー飲料などの機能性菓子を提案しました。そこに今回の「ぱくぱくプレキッズ」を加えれば、生まれてから未就学児までを網羅した品揃えが補完されます。特に父親はシリーズ商品をまとめ買いする傾向があるので、「ぱくぱくプレキッズ」のバンドル販売なども、提案すれば面白いと思います。
ロイヤルカスタマーづくりに一役買うベビーフード
製配販の情報交換通じ新カテゴリーの育成を
――新たなカテゴリーづくりは相応のエネルギーを要します。どのように啓発していくのでしょうか。
高橋 当社調べでは、ベビーフードの国内市場はおよそ300億円で、出生数を60万人と想定すると、一人当たり年間約5万円を支出する計算となります。しかも一品単価が数百円であることを考えれば、この期間の来店頻度は相当に高い。このようなカテゴリーは他になく、私自身も「ベビーカテゴリーのお客様は、長くお付き合いいただける大切な存在になる」と日頃から感じていました。「ぱくぱくプレキッズ」は、そのロイヤルカスタマーに、引き続き来店していただく動機付けになる商品だと考えています。
木村 リピート率、買上点数、購入金額の全てで他を上回るロイヤルカスタマーの獲得は、人口減と直面する日本の小売業様が抱える共通の課題です。ベビーのロイヤルカスタマーをプレキッズに導くことができれば、課題解決の糸口になるでしょう。
高橋 「プレキッズ」は海外で「トドラー」などと称され、欧米や中国で市場が確立されています。日本でもこれからの成長が期待されており、当社もフードの領域から地道に一歩ずつ認知度を高め、2030年までに市場を確立していく計画です。
「ぱくぱくプレキッズ」の認知向上策として、テレビ東京系列の人気番組「シナぷしゅ」とコラボした販促を展開しています。現在は、シナぷしゅのメインキャラクターと一緒に写真が撮れるイベントなども実施しています。シナぷしゅとのコラボCMも年末まで放映することが決まっています。
ただ、新カテゴリーの育成は当社だけではできません。ピップさんにもご協力いただき、半期に一度でも、製配販のキーパーソンとの情報交換の場を設けられたらと考えています。
木村 当社は展示会の会場で、主要得意先とカテゴリーリーダーを交えた情報交換会を実施しています。例えばアサヒグループ食品さんと思いを共にするメーカーにも参加していただき、ベビー売場の育成を目的にした情報交換などは検討の余地があります。ドラッグストア店頭でのコラボイベントなども、積極的に提案してほしいですね。
ノー返品契約結ぶ小売業も増える
返品率に応じた条件変更も検討余地あり
――先述したキユーピーの市場撤退は、返品問題にも一因があるようです。それぞれの立場でこの問題をどう捉えていますか?
高橋 返品は私たちメーカーに損失をもたらすだけでなく、原価に返品コストを上乗せすることで消費者にも負担を強いてしまいます。個人的にも、倉庫に積み上がった返品を見て、「これらの商品でどれだけの方の役に立てただろうか」と思うと、胸が痛みます。ただ、近年は社会全体で食品ロスやサステナビリティの観点から、ノー返品契約を結んでくれる小売業様も増えています。この機運がもっと盛り上がっていくことに期待しています。
木村 近年は食品業界でも返品削減が進んでいるのに、ドラッグストア業界には未だ返品の慣習が残っています。新カテゴリーの創造を目指しても、育成半ばで返品されれば水泡に帰してしまいます。精度の高い販売計画のほか、ノー返品契約や返品率に応じた仕入れ条件の変更などの工夫を皆で議論して、返品のない業界を目指す必要があると思います。
――貴重なお話をお聞かせいただきました。高橋様、木村様、ありがとうございました。

↓↓↓関連記事↓↓↓